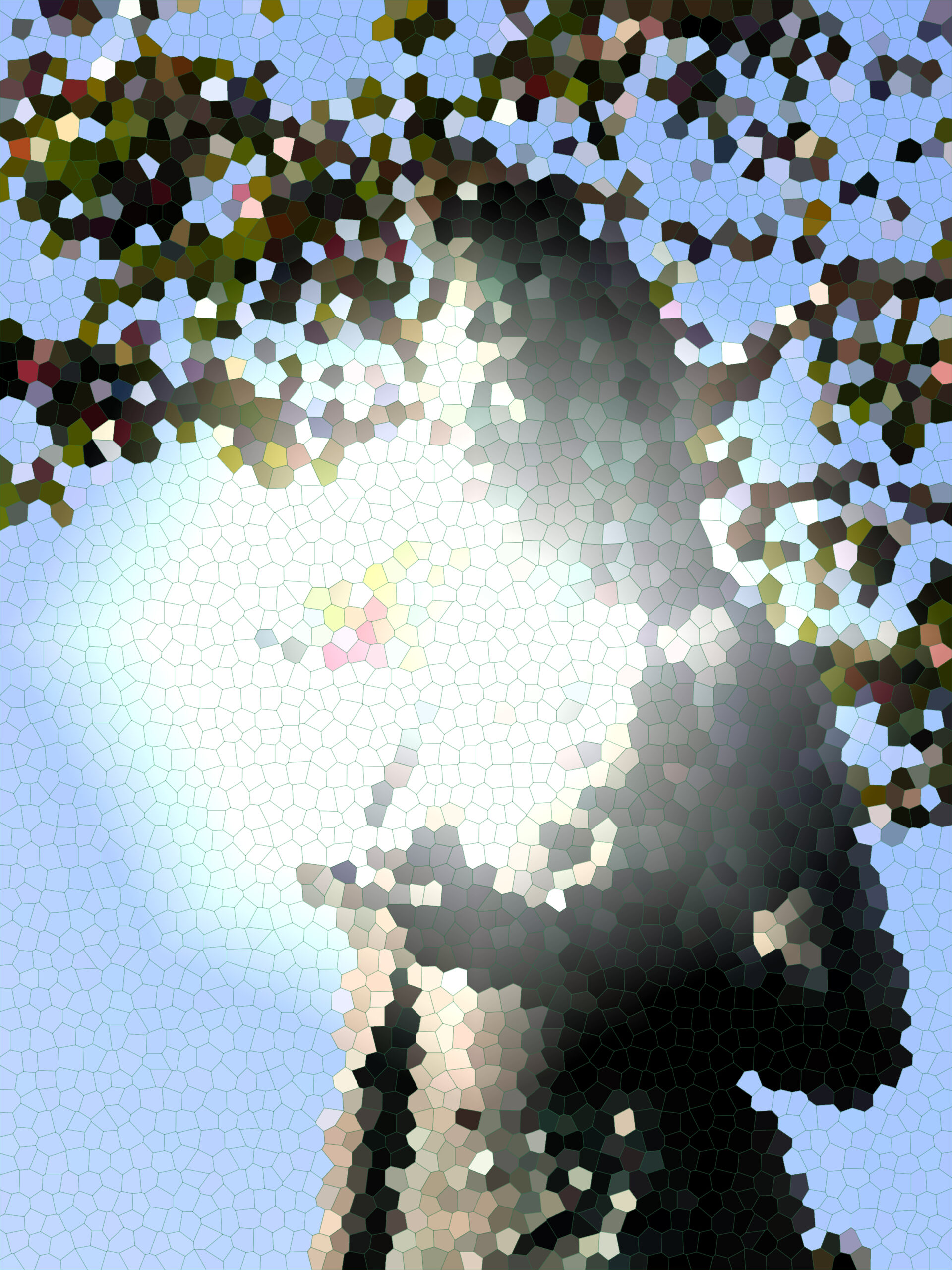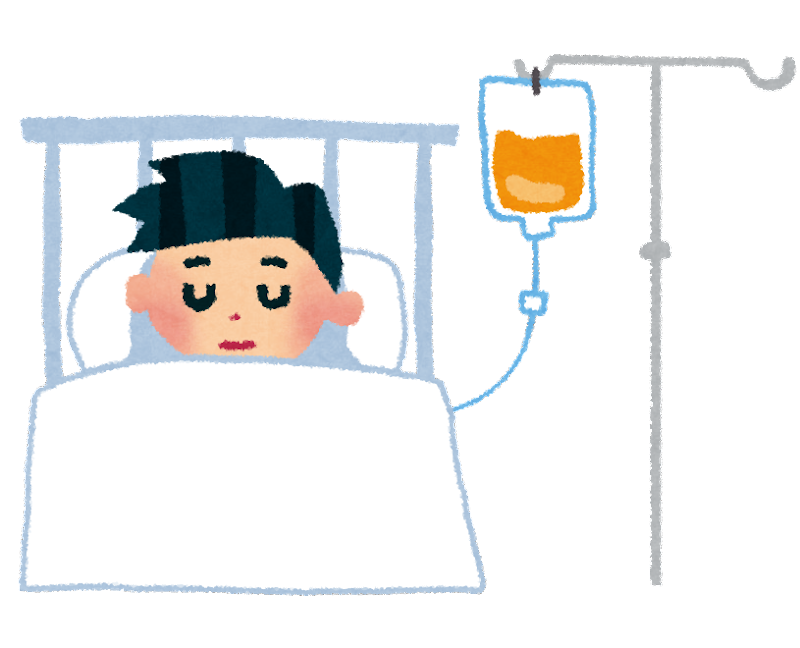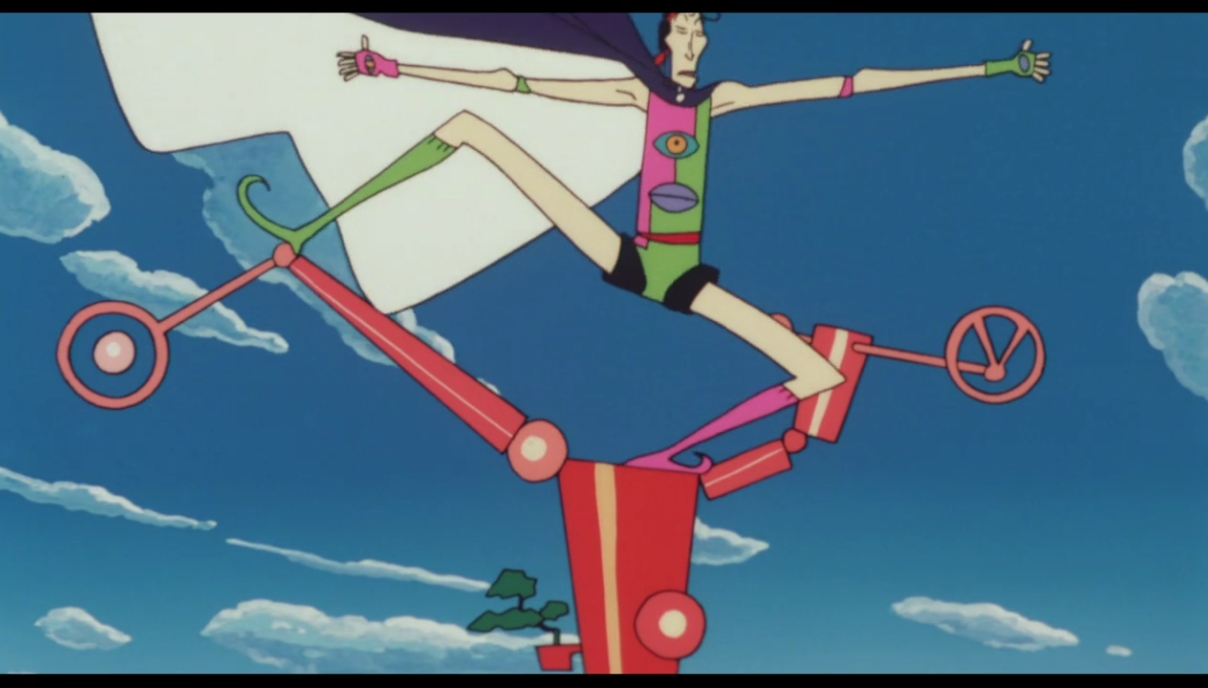ケムリクサも、けものフレンズも、たつき監督の脚本は10話以降の畳み掛け方が上手い。
初期の天才てれびくんのアニメのような少年の孤独な冒険奇譚の異世界雰囲気と、2000年代のKeyやサーカスの美少女ゲームのセカイ系奇跡ロジックを組み合わせているのがノスタルジーを誘う。
しかしケムリクサの主人公にメアリー・スー(※)を入れてしまったのはストーリーよくても失敗だった。
(※)メアリー・スー:作者や読者のネガティブな投影キャラクター。大半が自信がなくてオドオドしていて優柔不断。作品に投影する場合、読者や視聴者は自分の理想像を思い描くので、ネガティブなキャラクターを見せられると失望してしまう。結果、作品が大失敗する。
では本物の感動作品はどうやって作るのか?
感動の作り方
Keyもサーカスもたつき監督もそうだが、ミステリアスからの感動の構造を作るためにメインキャラクターを白痴(ドストエフスキー的な)設定にするので、どうも女性が感情移入しにくくファンタジー感が増しすぎてしまうんだナ。
2000年代において最も優れた感動作品は京都アニメーションのKey作品「CLANNAD」をおいて他はない。
泣く感動の構造として「罪悪感からの解放」がある。
つまりドストエフスキーの白痴のように最初から「弱者」を設定する。
あえて読者に見下げる「罪悪感」の視点と、子どもような「無垢」な視点による日常の当たり前の気づきの共有体験を促す。
その上で小さな奇跡や、出会いや別れを盛り込むとストーリーが出来上がる。
「本物の感動」は言葉では言い表せない「得も言われぬ気分」
「本当の感動」とは単に泣くことだけではなく「得も言われぬ気分」。
つまり言語ではまだ定義・表現し難いので感情が動かされるものをいう。
統計でいうと「外れ値」でなくてはならない。研究でも作品でもアートでも同じ。だから新規的な価値がある。
「本物の感動」とは「言語で定義できない定義域から外れた外れ値」
理不尽や不条理の非合理的な体験の反動で「突き動かされる何か」に後押しされ、徹底的に合理的・理性的になろうとする。
その得も言われぬ「何か」が良くも悪くも情を動かされた「感動」であり、「外れ値」としての起点となっていることが多い。
これは歴史的に宗教も革命も同じだ。
理不尽や不条理の設定としての「生老病死」
理不尽や不条理の設定として生老病死がある。努力でも避けられない宿命の問題。
お釈迦様のいう四苦である。
具体的には、「障がい、病気、子ども、高齢者、性別、人種、差別、貧困(≠貧乏)、孤立」などのことが付随する。
一般的に「弱者」と呼ばれるものである。
感動ストーリーを設定しようとすると、どうしてもこれらを盛り込む。
逆にいえば、障がい、病気、子ども、高齢者、性別、人種、差別、貧困(≠貧乏)、孤立など。一般的に「弱者」と呼ばれる方々を思いやれるかどうか?を見極めれば人生において地雷を踏んだり、巻き込まれずに済む。
例えば、「日銀総裁がETF買い入れして資金供給した」と聞いても別に何の感動もしないが、
「戦争によって障害をもつ病気で貧困の孤児メアリーちゃんが当たり前の日常を大切に必死に生きている」という話を聞かされた方がストーリーとしては感動するのである。
感動作品の作者は悪魔である
「感動作品の作者は悪魔である」と言われる理由は、
感動する作品を作る場合、作者は登場人物を「弱者」(障がい、病気、子ども、高齢者、性別、人種、差別、貧困、孤立)の理不尽な不幸状態に突き落とす必要があるから。
そこから日常の「当たり前」の幸せに気づき、日常回帰させる必要がある。
小説などの作品なら、まだ作者が理不尽に突き落とすのは恣意的なのでいい。
しかしリアルで弱者差別をやってくる奴はリアルにクズなので法の下の平等に引きずり出して合理的に裁きを食らわして一生日の目を見させないようにさせて良い。
俗に言うセカイ系だと、異世界転生してそのままハーレムの夢の世界で概念化するのが関の山なのでイマイチ痛みがない。
2010年以降のアニメは10話あたりで鬱回に入ったりすらない。
何も考えずに見れて良い。しかし成長はない。
例えば「この世界の片隅に」は日常の中での理不尽さを享受し、生活として一貫し、戦争や死という非日常があっても、また日常生活を貫徹しているのが凄味(すごみ)なのだ。
「この世界の片隅に」は日本アニメの転換点になる最高傑作(感想・考察まとめ)
2010年代において最も優れた感動作品は「この世界の片隅に」である。