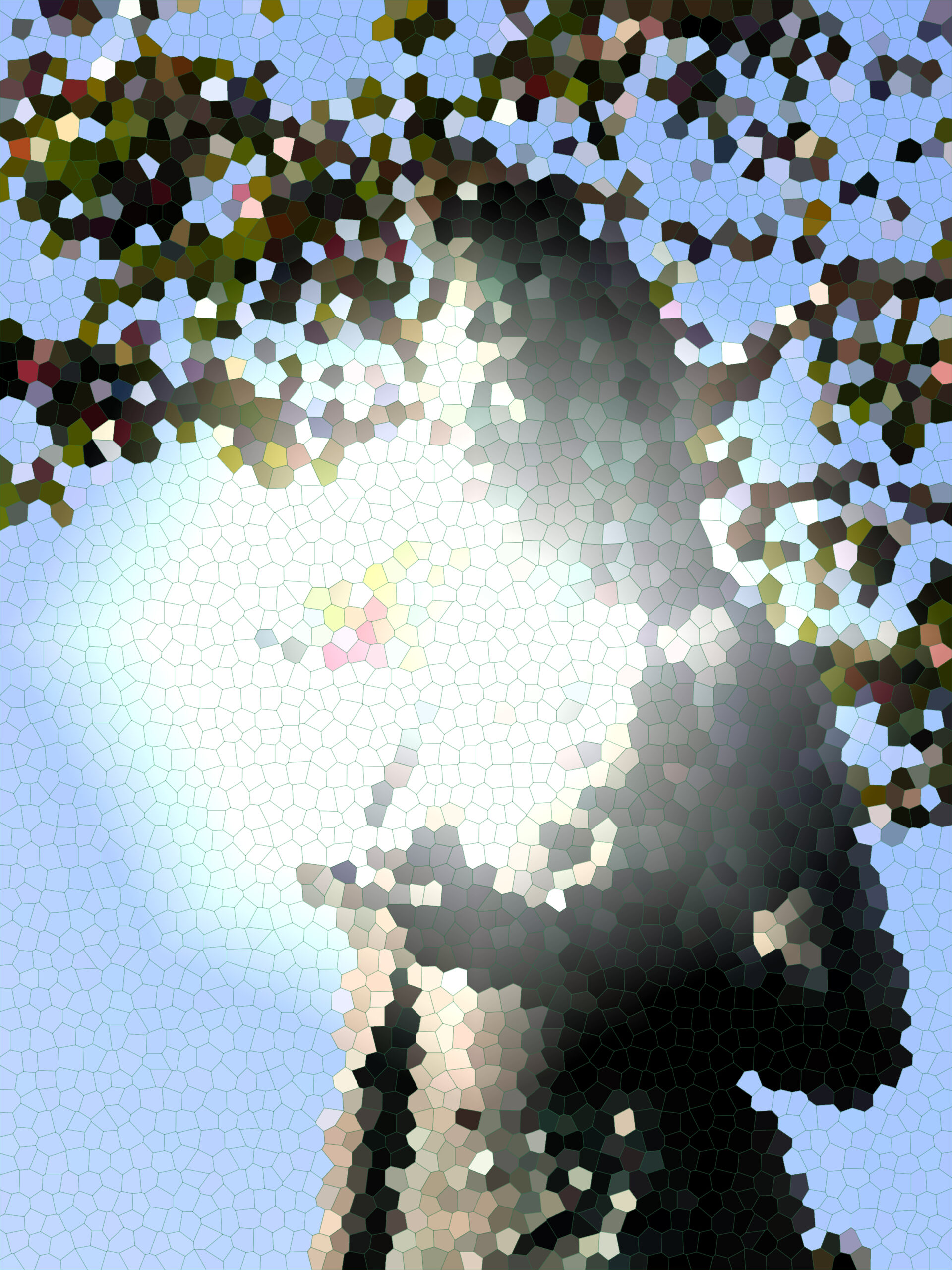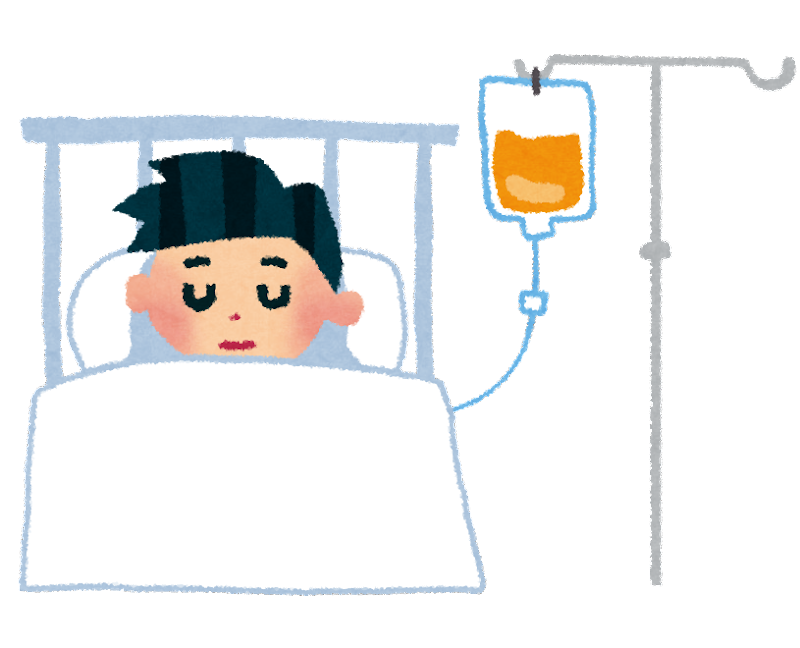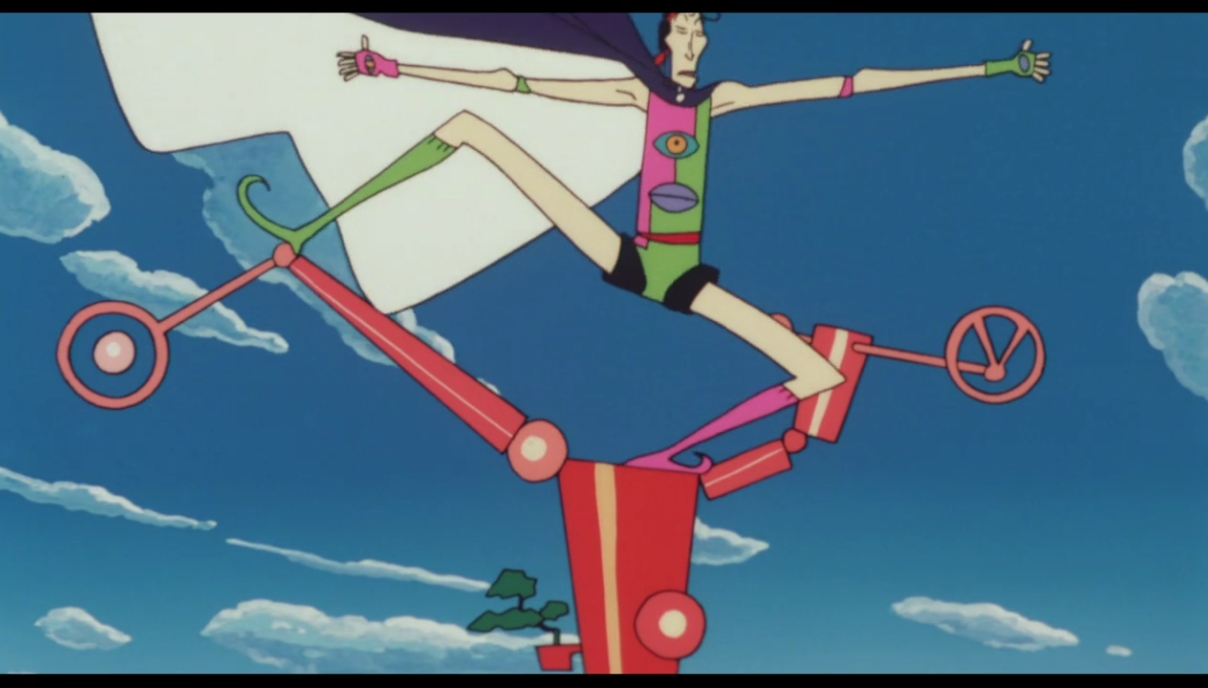の続きです。
例えば
「徳川次郎三郎源朝臣家康」を例にしてみよう。
松平竹千代→ 元信→元康→家康→徳川家康と改名。
苗字、字、氏、姓、諱の違い
徳川:苗字(みょうじ)場所
次郎三郎:字(あざな)通称
源:氏(うじ)身分や役割
朝臣:姓(かばね)氏族序列の地位称号
家康:諱(いみな)名前
構造的に格納されてる情報。
「姓」の序列
「姓」の序列は確固としてある。
真人(まひと):天皇や皇族
朝臣(あそみ):有力な豪族
宿禰(すくね):地方の豪族
忌寸(いみき):神事に関わる氏族
道師(みちのし):技術に関わる氏族
臣(おみ):有力な豪族、朝臣や宿禰の下位
連(むらじ):地方の豪族、朝臣や宿禰の下位
稲置(いなぎ):地方農民の統率者
上から順で「真人」は天皇家周りだけなので一般人にはまずいない。徳川家康でさえ朝臣である。
いつ今の形になったか?
1875年に明治政府により戸籍作成のため「平民苗字必称義務令」が出されてからは、
平民にも苗字が与えられ、
「字」は「諱」と統合されて名前になり
「氏姓(うじかばね)」の身分や地位は消えた。
近代化の立憲と自由民主主義のために強制的に特権を潰して平らにした勢いと潔さが凄まじい。
平等のためのデータベース化
明治当時は国民全員を紙に書き出して記録管理しないと
近代資本主義の「平等」(参加機会平等)の条件を選挙でも満たさないので「自由」が発動しない。
自由がないと「博愛」(神とのタテではなく、人間同士のヨコの契約)も起こらない。
スリム化したデータベース化。画期的。
ニックネームさえあれば良い
現代は通称(ニックネーム、ペンネーム)さえあれば、残りの情報はデータベースに格納されてるので通称以外がなくなっても認知は出来る。
ただその分、生体的なユニークさの個性を実力主義的に試されるので、後世に影響力ある爪跡を残そうと思うと厳しくなると。