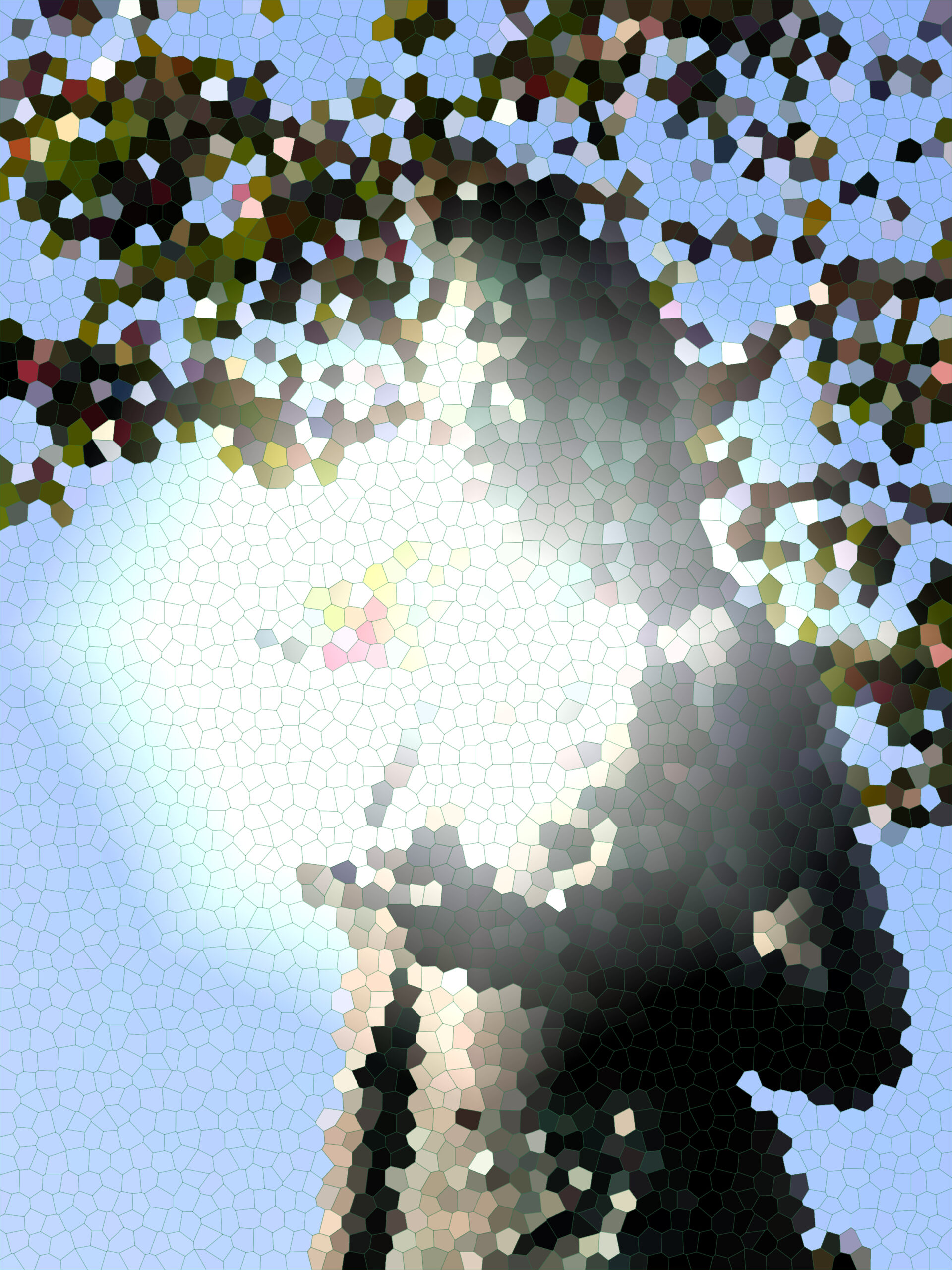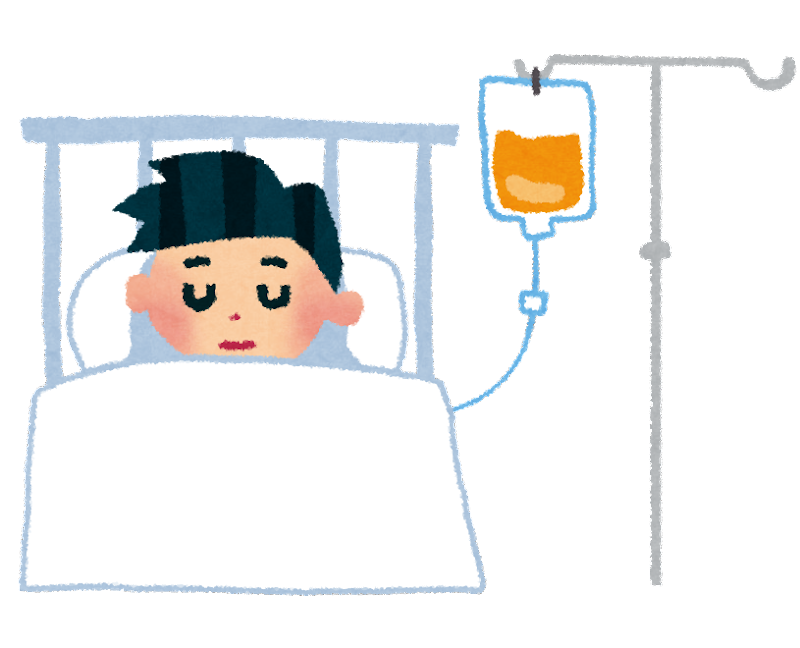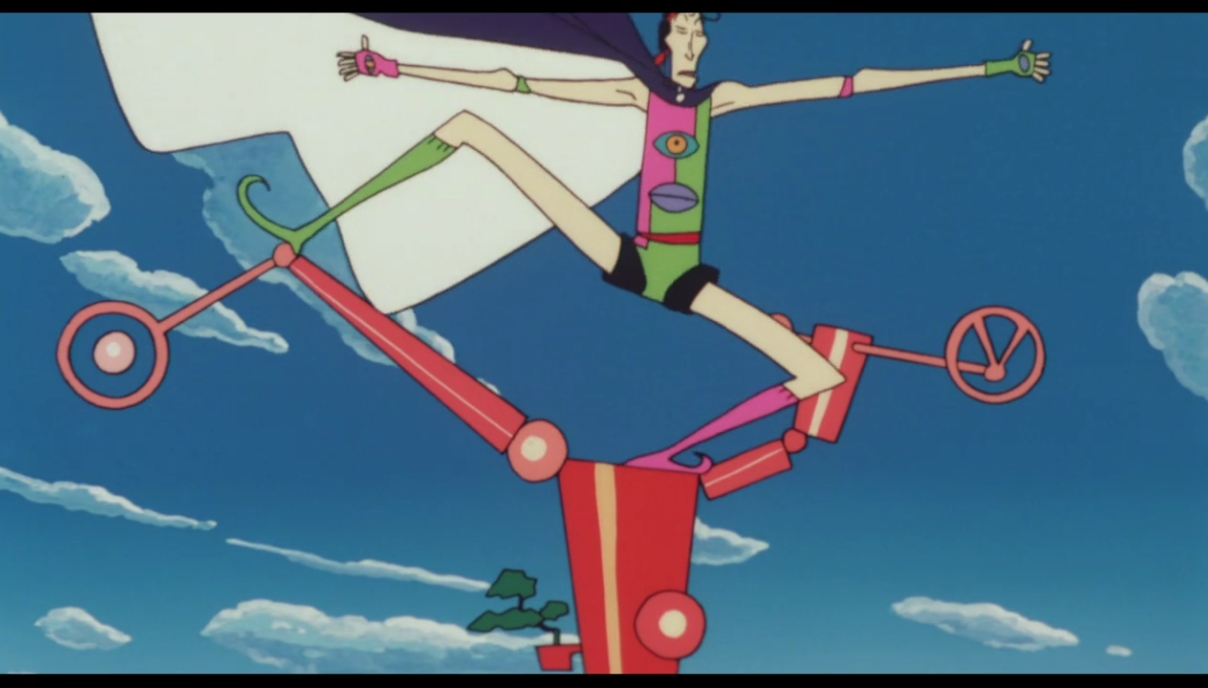ニーチェが尊敬し続けた600年前の神聖ローマ皇帝フリードリヒ2世や、
日本だと江戸時代の富永仲基(とみながなかもと)のような32歳にして逝去した未来を見通しすぎた大天才。
再発掘もされず、歴史に埋もれてるのが可哀想すぎる。
幕末から戦前の日本人が、語学表現においても思想においても極まりすぎてて原点にして頂点の最高峰。
しかし難しすぎて紐解ける人が少なすぎる問題。
戦前の復古運動を正しく理解してキャラ確立してる人が本当にいない。
令和が鎌倉時代を模写してるため、中国に占拠される中で、アートは運慶快慶のように奈良時代や平安初期(天平・貞観)へ復古しないといけない。
その上で、日本独自で、足利義満の金閣・能・水墨画の唐折衷の北山文化や、足利義政の銀閣・書院・枯山水の禅折衷の東山文化を。
インバウンドで中国人に買い叩かれる日本と、
明の銅銭(永楽通宝)が流通しすぎてしまう室町時代と似すぎてて足利義満。
200年間続いて、寛永通宝の江戸時代に中止されても更に200年間野明治時代まで続いた。
今後はデジタル人民元。
鎌倉時代以前までは僧侶は政府から認められた第一種国家公務員だったが、
親鸞革命と日蓮革命により、南無阿弥陀仏と南無妙法蓮華経で悟れる「誰でも出来る」となって民衆へ一気に広まった。
今のプログラミングや創作のAI革命と同じ。
そして中国に室町インバウンド政策をした足利義満。そして戦国へ
「婆娑羅(バサラ、当時の大陸のダイヤモンドのようにド派手という意味)だ!」と大陸文化にかぶれた土岐頼遠や佐々木道誉等の大名が闊歩し、戦ばかりの悲劇で収拾つかなくなり200年。
「うつけ」の織田信長が出てきてカリスマパワーでやっと天下統一。
「歌舞伎」で喜劇として風刺されるまで100年。
「歴史に名を残すことの出来る地合い」ではあるが、人間と変化の新陳代謝が激しすぎて、それやる人は寿命が短くなる。
大河ドラマでも人気の戦国時代と幕末時代の特徴。